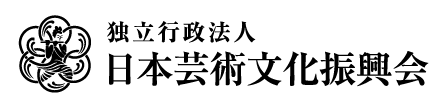国立劇場第164回 舞踊公演 「舞の会-京阪の座敷舞-」(11月21日) 特別対談【前編】
児玉信(前石川県立音楽堂邦楽アドバイザー) & 林慶一(d-倉庫)
国立劇場の秋恒例「舞の会―京阪の座敷舞―」。令和2年度はコロナ禍で開催が危ぶまれたが、例年の2部制を3部制にし、公演時間や換気などに最大限の配慮をした上で無事、開催された。京阪の花街のお座敷を中心に、独特の発達を遂げた「座敷舞」は、今も東京で見る機会が限られ、本公演も上方四流(井上、楳茂都=うめもと、山村、吉村)の踊り手が揃う、貴重な機会となった。国立劇場開場翌年の昭和42(1967)年から続く同公演について、邦楽プロデューサーで前石川県立音楽堂邦楽アドバイザーの児玉信さんと、東京・日暮里の「d-倉庫」でのダンス企画で、大きな存在感を放つ林慶一さんが語った。座敷舞とコンテンポラリー・ダンス、ジャンルを超えて話は広がった。
児玉信
林慶一
「舞の会」開催の意義
児玉(以下、児):私はこの「舞の会」を非常に楽しみにしている一人です。上方舞は歌舞伎舞踊などのいわゆる日本舞踊に比べると、公演数自体が東京では少ないように思われるから、私のような無精者には見る機会も限られてきます。京阪の座敷舞を各流派の人と曲をまとまって見られる、得難い催しだと思っているのです。
今は地方の公共ホールも和物に向いてない仕様が多く、また舞踊公演は経費がかかる割に集客率も上がらないというので、減少傾向にあります。企画する側の人材もなかなか育ちにくい現状ということもあるでしょうが。そういう意味でも、公的な国立劇場の責任は重いと思っていますし、是非、継続してほしい企画です。ただどうしても出演者の顔ぶれが固定しがちなので、若い舞踊家の掘り起こしに留意してほしいですね。それと若い観客の掘り起しです。潜在的に上方舞や日本舞踊を見たい人はいるはずです。なんとか新しい観客を増やしたいと及ばずながら思っています。どうしたらいいか、解決策はなかなか見つからないでいるのですが。それはともかく、今回はコロナ対応で3部制になりましたが、曲目数は昨年と変わらず12曲でした。数年前と比べると曲数が増え、それが若手や新人の出演にもつながっているように思えて、とても良い傾向だと思っています。
林:僕はこの「舞の会」を、令和元(2019)年から続けて拝見しています。僕が関わっているコンテンポラリー・ダンスとは全く違う世界ですので非常に新鮮で、発見も多いですね。
公演を振り返る
【12時の部】
〈3部制の最初は、いずれも地唄。遊女が琵琶湖の水面に映る自身を眺め、恋を思う「水鏡」(吉村章月)、独り寝の女の寂しさを描く「袖の露」(井上豆弘)、春の京の風情を伝える「東山」(楳茂都梅衣華=うめきぬはな)、能に取材した「善知鳥(うとう)」(山村友五郎)が上演された。唄・三味線で人間国宝の富山清琴が出演するなど、当日は地方(演奏者)も豪華な顔ぶれだった〉
袖の露(井上豆弘)
林:井上豆弘さんのように、流派から新しく出てきた方も、この「舞の会」という大舞台に上がれることは、素晴らしいと思いました。
児:出演する舞踊家さんの誰もが、この会をすごく大事に思っている。そういう張りつめたものは何時も感じています。特に若手や初めて出演するみなさんは、お師匠さんに相当しごかれてもいるでしょうね。そういう初心に溢れた舞を観ることも出来るのは、一種の眼福です。それがこの会を観る楽しみの一つであると私は思っていますけどね。
林:楳茂都梅衣華さんの「東山」がよかったですね。ポーズをパッと見せるのではなく、小さい動きの連続が踊りになっているということを、改めて感じさせました。ダンス的な線の大きな動きと違い、もっと細かい運動で楽しませてくれました。単純に格好良かったですね。

東山(楳茂都梅衣華)

善知鳥(山村友五郎)
児:山村友五郎さんの「善知鳥」は同名の能を典拠とする曲で、吉村流では奥許しと聞きますが、これを友五郎さんが3年前、新たに振付けて初演されたというものです。大阪の大槻能楽堂でのことでしたが、私は御案内をいただきながら伺えませんでした。残念に思っていましたから有難い機会でしたが、新振付というわけだけれど、だいたいが何時も漫然と舞台を見ているだけのいい加減な鑑賞者なので(笑)頼りにはならない。まあ屁理屈ですけど、新振付を標榜するといっても、曲を知らない人にとって、新振付とは何か、という意味合いも含め理解はなかなか難しいのではないですかね。そう思って見ていました。初めて見る人には多分、違いが分かりません。私にしても結局、舞としてどうだったかに落ち着くことになります。流儀に新たな財産を加えていこうとする積極さや、能舞台で初演したものを平舞台にかけてさらに彫琢(ちょうたく)していこうとする友五郎さんの姿勢はずっと注目しています。
【午後2時半の部】
〈続いて、様々なからくり人形を舞い分ける地唄「からくり的」(吉村松韻=しょういん)、廓の男女を描写する上方唄「世界」(山村光)、恋に憂き身をやつす女の地唄「影法師」(神崎えん)。地唄「鉄輪(かなわ)」(井上八千代)は、同名の能を原作とし、夫に捨てられた女の悲しみや激しさを描く〉
鉄輪(井上八千代)
児:井上八千代さんが「鉄輪」を、東京では初めて鬘を付けずに地髪で演じたというのが私にとってはうれしかったですね。先代(四世)八千代さん(1905~2004年)の舞姿も思い出されます。道行を舞うことも考えたが、当流独特の笠を使ったいい振りがあるのでそれを採用した、とプログラムに述べています。本業の能の前半は、自分を捨てて新しい妻を持った男への恨みで貴船明神に願掛けした女が、笠を被って顔を隠し密かに通う、それを踏まえた振りなのでしょうね。能では笠を取った女の髪が俄かに逆立つという、形相すさまじい態で揚幕に駆け込みますが、京舞の方はむしろふっと消えゆくみたいに風情を感じさせるところがあって、これもいいなあと。
林:今回、舞の中で跳躍をされていたのは、八千代さんだけではないでしょうか。元(2019)年の公演でもやっていたと思います。あれは井上流の専売特許なのか、動画で先代の踊りを拝見したところ、やはり跳んでいました。
児:舞は「回る」が語源とも言われるから、なかなか踊りのように「跳ねる」がない。だから跳ぶと「おおっ」と驚くというかね(笑)。京舞の「鉄輪」では何度か跳びますね。能では「いつまでも一緒だ」と約束した男の嘘を見抜けなかった自分も悪いが、それにしても悔しい、と女は述懐します。あの世に行ってからでは遅い、生きながら鬼になって、この世で復讐したい、そういう積もり積もった女の恨みの発露が、あの跳ぶ所作に凝縮するのかと思います。美しく見える振りだけど実は怖い。
林:神崎えんさんは、今回はお父様の振り付けだったと思いますが、昨年と印象が違いました。伝承の中に創意がありますね。
影法師(神崎えん)
【午後5時の部】
〈新振付作品が並び、井上安寿子(やすこ)が井上流にない曲に振り付け、舞う地唄「鐘ヶ岬(かねがみさき)」に続き、遊女の心情を山村友五郎が振り付けた地唄「かくれんぼ」(山村若有子=わかゆうこ)。男との逢瀬を情感豊かに表現する上方唄「ぐち」(楳茂都梅咲弥=うめさくや)、軽妙さも交え夫婦を描く上方唄「三国一」(吉村輝章=きしょう・吉村輝之)が続いた〉
児:井上安寿子さんには平成22(2010)年、私が企画制作に携わっていた石川県立音楽堂で(京舞の)「お七」を舞ってもらいました。その折、(人間国宝の能楽師)片山九郎右衛門さん(=幽雪、1930~2015年)がご夫婦で見に来られた。「生きているうちに孫の『お七』を見られるとは思わなかった」とおっしゃったのが忘れられません。彼女も、あの舞台で自信がついたかもと思いますが、企画者の立場からすると、この人に、この曲をやらせてみたい、見てみたいという思いを抱かせる演者がある。あの時の彼女がそうでした。活躍ぶりが嬉しくて、期待しながら見ていました。
鐘ヶ岬(井上安寿子)
ぐち(楳茂都梅咲弥)
林:今回、私が非常に関心を惹かれたのは、楳茂都梅咲弥さんですね。「ぐち」という作品でしたけれども、まるで震えているような、ずっと細かい動きをされている。遠目には止まって見えるシーンでも、ほんとうに静かに首や全身を動かし続けていました。それは日常の不随意運動を模しているのとも違って、僕からは異形の美に見えたんです。
1950年代末から1980年代にかけて日本の前衛舞踊史にセンセーショナルな足跡を残した土方巽(ひじかた・たつみ、1928~86年)という舞踊家がいます。彼の舞踊は「暗黒舞踏」とよばれるもので、その実験は多岐にわたり一概に説明できませんが、今回、梅咲弥さんの舞を見て想起したのは、土方の1972(昭和47)年の「疱瘡譚(ほうそうたん)」という作品です。土方がそこで示したのは、健康で美しい身体の躍動ではなく、立つこともできず、腰を地面に据えて、四肢が空をまさぐるようにざわめき続ける、「踊る」という行為に対して非常に反省的な、奇異な身体のありようです。土方のように確信犯的な逸脱とは異なりますが、梅咲弥さんの微細な動きの連続が、僕にはとても異様な姿として映り、そこに「疱瘡譚」の土方を重ね合わせて見ていました。実際には意図した運動ではないかもしれないし、偶然かもしれませんが、衝撃的でした。
あとは山村若有子さんの「かくれんぼ」も印象に残りました。友五郎さん振付ですが、衣裳がどういう風に動いていくか、自分自身を観察されながら、繊細に踊っておられた。妖艶で、着物の動きまで舞になっているようでした。
かくれんぼ(山村若有子)
林:(劇場ではなく)座敷で見なければならないと思わせるものが、「舞の会」にはありますね。もっと近くで観たい、と思わせる魅力です。それは実は小劇場文化も同じ。最大50人ほどの小空間で見る作品と、大きい空間で観る作品は、創作段階からやはり違う。しかし観客を多く入れるため、改変される。小劇場で生まれたダンスや座敷舞の魅力は本来、繊細で微細な身体の運動が堪能できるところにあると思います。非常に贅沢ですけれども。
児:もっと近くでという小劇場文化のお話、私には新鮮です。よく「息遣いが聞こえる」という表現をしますが、座敷舞はまさに裾を引いた衣裳が畳と擦れ合う音を、「いいな」と思う。それも楽しさの一つです。
コンテンポラリー・ダンスとの比較
林:日本のコンテンポラリー・ダンスが独特なのは、踊り手が同時にダンス作品の作者、つまり振付家でもあるケースが多いことです。他の振付家の作品に踊り手として参加しながら、自らも独自に作品を振付・創作して発表する。コンテンポラリー・ダンスは作品主義の世界ですから、振付家や作者として認められないと、個人として社会的な評価を得ることが難しいためです。「あのダンサーよかったね」と言われても、最終的には評価は振付家にあるんです。
舞踊の教育や訓練などを経ずに、創作する人もいます。作品主義ですから、極論すれば技術が無くともコンセプトだけで作れる。2000年代の半ばまではそういう作品が多く認められましたが、今は小さい頃からモダン・ダンスやバレエを習い、大学に入ってコンテンポラリー・ダンスと出合い、自身の創作を始めたり、他の振付家の作品に出演する方が多いかなと思います。日本の伝統芸能の世界では、まず舞台上の踊り手に注目するのが、いい所だと思います。
「舞の会」の観客の声に耳をそばだてていると、芸事に関わっている方が多く、客席で挨拶回りをしていますね。いわゆる〝お稽古文化〟が息づいている。お稽古文化はコンテンポラリー・ダンスの世界では、批判的に言われる事が多かった。しかし、人々の社会的な営みと乖離して行われる傾向にあるコンテンポラリー・ダンスの状況を日々見ていますと、むしろお稽古文化には多くの可能性が秘められているのではないかと感じています。踊ることも、踊りを観ることも我が事として主体的に味わうのが、芸を楽しむ神髄ではないか。実は、コンテンポラリー・ダンス公演の観客も多くが踊り手です。
児:今のお話しには、基本的な技術の習得を目指す、いわゆるレッスンと、先ほど奥許しという言葉を口にしましたけど、曲に「重習(おもならい)」とか「平物(ひらもの)」というように階梯をつけて来た伝統芸能の習い事、つまりお稽古とのニュアンスの違いを改めて感じました。主体的に楽しむというと、例えば「謡曲十五徳」を思い出します。行かずして名所を知る、薬無くして鬱気(うつけ)を散(さん)ず、旅にありて知音(ちいん)を得るなど、謡の稽古には十五の徳があるというものです。まあしかし、話がいささかズレるかと思いますが、このところ日本舞踊に限らず、能でもお稽古をする人が減っています。お師匠さんがお稽古の収入で生活する、というモデルが成り立ちにくくなっている。昔は子供に踊りを習わせることもけっこうありましたが、今は親世代も日本舞踊を知らない。お稽古の需要が減れば、お師匠さんも減る。特に地方でその傾向が強いのではないでしょうか。現今はヒップホップダンスに乗っ取られてしまった感があります。日本舞踊にもヒップホップの要素はあるんだから学校の授業でも取り上げて欲しい-と嘆いていますが多勢に無勢で通らなさそう。残念です。

林:日本における現代舞踊は大正期、ドイツの新興舞踊をルーツとして立ち上がり、戦前は前衛的な役割を担っていたと思います。しかし戦後、全国規模の業界団体として現代舞踊協会が組織され、加速度的な普及の結果として「習い事化」が進んでいったものと僕は理解しています。戦後はお稽古事としてのバレエ文化が急速に人口に膾炙(かいしゃ)していきますから、これに対抗する必要性もあったのでしょう。舞踊家が主宰するお稽古場(舞踊研究所)は、実演家としての経済的基盤を確保する上でも生命線となるものですから、維持のために様々な工夫と妥協が生じたものと思います。結果として研究所の創作活動が保守化せざるを得なかった側面も少なからずあったでしょう。しかし、そのような世間の感覚との折衝を保っていたこと自体は、芸術という閉鎖的になりがちな領域において非常に興味深い事態でもあります。必ずしも新しいものを作ることが芸術の役割ではありませんから、ここには別の視座も立てられるように思います。
日本のコンテンポラリー・ダンスにおいては研究所や「お稽古場」といった拠点は失われつつありますが、振付家はダンススタジオなどのゲスト講師として招かれ、ワークショップを行うことはありますし、僅かですが自前のスタジオを有する方もいます。コンテンポラリー・ダンス専門の教育機関というのは日本にはありませんから、そのようなワークショップで同分野の考え方を吸収し、そこから独立して活動する人たちも少なくありません。斯界においては、作者として舞台に登場した途端、それぞれ家元(笑)。振付家としての最低限の尊厳が認められます。
児:30数年近く前、私は謡本の発行元に勤めていました。そのため何でも能と結びつけて考えるのが悪い癖ですが、もう亡くなった社主が、「昔は世の中が不況になると謡の稽古をする人が増えたものだが、今は世間の動向と同じで不況になれば謡本の売り上げも減る」と言ったことがあります。今度のコロナ禍では、不要不急の外出は自粛して欲しいという通達があって、伝統芸能の若い担い手たちの中からも「自分たちの芸は必要ないのではないか」と、将来を悲観するような発言が出ました。これも昔、明治生まれの能の重鎮シテ方が、「自分たちの若いころは山あり谷ありだったが、今の若い連中は山ばかりで、どん底を知らないから、そうなったときが心配だ」と言っていたのが思い当たります。
最近、能楽協会の現在の会員数が約1100人と知って驚きました。私が能の世界に身を置いていたころは1500人ぐらいと認識していましたから。それは能界を下支えしていた享受層も薄くなっているのと軌を一にすると考えざるを得ません。能楽堂に行ってみると観客自体は増えているように思われますが、稽古してくれる層がいなくなるのは、伝統の継承という面で危機感を覚えます。
それと今の、それぞれが家元というお話しでは、いわゆる新舞踊を思い浮かべました。日本舞踊にとって新舞踊の隆盛を脅威に思っていましたが、その新舞踊でも愛好家の高齢化が進んで門下が減り始め、将来的な経済不安から足が遠のき始めているという報告があります。
そこへ持ってきてのコロナ禍です。全ての芸能にとって今どうあるべきか―、悩ましいです。暗い話になってすみません。
編集:飯塚友子(産経新聞記者)
※写真撮影時のみマスクを外しました。
※後編はこちら。
プロフィール
- 児玉信(前石川県立音楽堂邦楽アドバイザー)
- 静岡県生まれ。大学在学中から折口信夫の提唱により設立された藝能学会に入り、機関誌『月刊藝能』(現『年刊藝能』)の編集に携わる。その後、観世流及び金剛流の謡本を発行する檜書店に入社し、観世流機関誌『月刊観世』の編集を担当。能楽のほか舞踊や邦楽公演の企画、執筆など幅広く活躍。藝能学会副会長。近著に『能舞台歴史を巡る』(2018年、建築画報社)。
- 林慶一(d-倉庫)
- 埼玉県生まれ。制作者。2006年より小劇場die pratzeにスタッフとして参加。2005年~2015年は自身のパフォーマンス活動を併行して行う。2012年より「ダンスがみたい!」実行委員会代表。同年、d-倉庫 制作。アーツカウンシル東京 平成29年度アーツアカデミー事業 調査研究員(舞踊分野)。2019年「放課後ダイバーシティ・ダンス」プロデューサー。