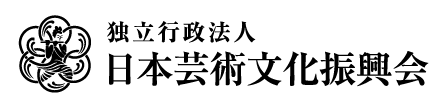国立劇場第164回 舞踊公演 「舞の会-京阪の座敷舞-」(11月21日) 特別対談【後編】
児玉信(前石川県立音楽堂邦楽アドバイザー)& 林慶一(d-倉庫)
日本舞踊にとどまらず能楽など広く伝統芸能界を真摯に見つめ、普及や振興に心をくだく邦楽プロデューサーの児玉信さんと、公演やフェスティバルの企画・制作等を通じて幅広くコンテンポラリー・ダンスに精通するd-倉庫の林慶一さんによる対談の後編。日本舞踊とコンテンポラリー・ダンスの違いを軸に、それぞれが抱える課題や、新作や批評をめぐる様々な論点など、話は尽きることがありません(前編はこちら)。
新作への期待
児玉(以下、児):本公演では山村友五郎さんと、井上安寿子さんが新たに振付した曲がありました。プログラムに新しい作品が加わることも大事だと思っています。その新作品の作者ですが、昔は文学者といわれる方たちも関わっていますね。現代にもこういう機運があっていいと思うことがあります。具体的に何方にお願いしたらとまでは思いつきませんが。言葉に美しさがあってしらべがあって・・・そういう作品がいいなとは思います。
林:言文一致に関わる動向はありますか。
児:口語体の作品はありますね。でも耳慣れないせいもあるでしょうが、口語はどうも伝統芸能とは未だしっくりこないような気がして。
林:歌としての響きが損なわれてしまうから、大きな壁がありますね。
児:古文なら短く済むところが、口語だと同じ事をいうのにも字数が膨らみそうで・・・。
林:素人目には、古文は外国語に近く、翻訳が必要ですね。しかし詞章の意味がわかれば良いというのは短絡で、様々な実験が必要なのだろうと思います。コンテンポラリー・ダンサーと日本舞踊家や能楽師が競演する舞台もしばしば行われますが、一過性の取り組みにせずに、それがそれぞれの分野にどう還元されるかの方が重要。その展開に注目しています。
児玉信
児:能の世界では近年、上演が途絶えた作品を見直す「復曲」が注目され、現行の曲でもかつては行われていた演出に光を当てるというようなことも行われました。その流れの中で新作が生まれる機運も醸成されたかと思います。学者との共同作業が顕著であることや、女性作者が誕生したのも、能の新時代を感じさせます。
能は現行曲と言われる主なレパートリーが250~300近くあり、新作にはそれらには無い新たなテーマ性も求められることになります。また新規を求めて様式をあまりに踏み出すのでは能ではなくなってしまう恐れもあるから、その点は日本舞踊の方が自由かな。
思い出すのは八世観世銕之丞(てつのじょう、1931~2000年)さんが、「三山(みつやま)」という宝生流と金剛流で演じられる曲を昭和60年12月、観世流として復曲した時のことです。初演舞台を拝見したあと銕之丞さんにお目にかかる機会があり、「ごちゃごちゃした印象だった」と感想を述べたら、「最初は考えられるかぎりの型を入れなくちゃ、後で削れないんだ!」と叱られた。現行曲は削って、削って年月を経て、今、ここにあると、肝に銘じている話です。新作を手掛けることは、今ある作品がどういう経過で今ここにあるかを知る意味でも貴重な作業だというのですが、エネルギーのいることだし、再演の機会も多くは持てない。今はかなり自由になりましたが、以前はそれをやれる人も限られていました。見ている方は気楽ですが、作る方はなかなかね。皆さん、よくやっているなと思っています。
林:私共の劇場(d-倉庫)のダンス・フェスティバルでは、例えばストラヴィンスキーの「春の祭典」などと課題曲を決め、参加する振付家それぞれに作品化してもらう特集を組んでいます。なぜそういう企画をするか。日本のコンテンポラリー・ダンスは基本的に新作の上演で回っています。著作権の問題もありますが、歴史的楽曲への挑戦というのはごく僅かです。新作主義はコストもかかる上、歴史性への意識が希薄になりやすいんです。そこに反省的に目を向ける機会が必要、と考えて企画しています。
伝統芸能の世界はまず作品があって、それをどう料理するか、純粋に舞踊家の姿勢が注目されますね。作品に挑戦した先達の息吹が脈々舞台に刻まれており、その中で現在の踊り手の姿が立ち現れる。
児:新作でいいものを、次に繋げていく。そのためには、他者に踊ってもらうことが必要だと思います。今回上演された曲もみな、そうやって振りを移され、繋がってきということですよね。でも舞台に現れるのは全く同じではない。
世界(山村光)
林:面白いのと思うのは、やはり人が器になる以上、継承の過程で、どうしても間違いも生じるし、違う人が受け止めれば、違う形にもなる。でもそれでいいと思います。世代を跨ぎ、人と人の間になされる芸の継承におけるダイナミズムは僕には縁遠いもので心惹かれます。
明治期までの歌舞伎(舞踊)が文化的先鋭であったことは言うまでもありませんが、大正時代には洋舞に学んだ日本舞踊における新舞踊の展開も現代舞踊に拮抗して活発なものでした。しかし日本においては戦前戦後を境にして日本舞踊は静的な伝統として見なされるようになってしまった。近代的な捻じれといえばそれまでですが、歴史に対する連続性の担保と、今日行われる必然性を問う新局面の開拓という視点から言えば日本舞踊も、コンテンポラリー・ダンスも本質的には同じミッションを携えて行われているのではないでしょうか。伝統と創造を分け隔てて自明視する視点こそが批評的に顧みられるべき局面であり、僕自身にとっても重要なテーマです。
林慶一
児:伝統という時、みなさん形がカッチリ決まったものと思われる。一方で、変えてきたからこその伝統だ、という考え方もあります。常に変化して生き残ってきたからこそ、伝統ですね。能の場合、型が出来上がっているから、その通りやればそれらしく見える。でもそれだけでは能にならない、と言われることがあります。
片山九郎右衛門(幽雪)さんが、自分の体験としておっしゃったことがありました。観世流の型付としては足を二足出す所で、「舞っていて自分としてはどうしてももう一足、出たい。そういう時がままある」と。演者の気持ちでもう一足出るのは許容の範囲ということは、型はあるけれども、ないとも受け取れるかとも思います。伝統芸能には、そういう自由さもあるのではないでしょうか。絶えず呼吸している。
林:日々の生活の中に息づく、伝統と意識さえしないものこそ「伝統」であるという考え方がありますね。それは血肉化されて日々、変わり続けている。そういうことへの気づきを与えるのが、伝統芸能かもしれない。骨董品のように古典を愛でるだけでなく、自分自身や生活の中に伝統を発見して関わろうとする意識を持つ。日本舞踊には、そのヒントが含まれている気がします。
水鏡(吉村章月)
からくり的(吉村松韻)
伝統芸能ならではの楽しみ
児:金沢では、(振付家・ダンサーの)森山開次さんと仕事をしたこともあります。石川県立音楽堂はオーケストラアンサンブル金沢のフランチャイズでもありますが、金沢素囃子保存会との共演などもあって洋邦のコラボレーションをやりやすい環境にありました。森山さんには石川県ゆかりの能を題材にした『UTAURA』(『歌占』)ほか何作かを作ってもらいました。全部、和洋楽器などの混用です。『歌占』は和歌を記した短冊を依頼人に引いてもらい、依頼人の悩み事を解決に導く男神子(おとこみこ)がシテです。森山流の『UTAURA』は箏を二面、短冊に見立てて、奏者ともども舞台と花道を移動させたりしました。その間を縫うように森山さんが踊るのですが、奏者も初め戸惑いを隠せなかった発想は目から鱗でした。でも、これは何時でも思うのですが伝統芸能に携わる方たちの適応力というのもすごいなと思いますね。懐の深さを感じています。『UTAURA』は作品としても面白かったと思うのですが、集客がイマイチだったのが心残りです。お客さんに新作への興味を喚起するのが難しかった・・・。
林:東京というのはやはり特殊な条件下にあって、複雑な文脈を共有できるコミュニティを前提にして舞台も行われていますよね。首都圏から出ると、それを気づかされる事もあります。
児:文楽の地方公演も、集客が難しいという話を聞きます。金沢では隔年に文楽公演を持ちましたが、「曽根崎心中? 前に観た」の一言で片づけるお客様がいる。「今度は人間国宝が出演します」と言っても響かないこともありました。舞台は一回一回が違うと思って頂きたいけれど、お手上げでした。でも、いい経験だったな。
林:伝統芸能の面白さって、繰り返し同じ演目を見る時の気付きにあるような気がします。若い頃、いわゆるクラシック音楽を聴いても全然分からなかったのですが、ある時、同じ曲でも指揮者や楽団によって印象が全然違うと気づいた。ああ、こうやって楽しむものかと気づきました。伝統芸能も同じですね。
この演者はこうやるのか、この作品はこういう演出だと全く違って見えるとか。そういう発見をし、目が肥えていくと感じる瞬間は楽しいです。
児:伝統芸能を見る大きな楽しみの一つだと思います。ああ、この曲にこんな解釈があるのかとか。東京だと色々な舞台を観ることができ、比較対象化がしやすいと思いますが、地方だと公演機会が少ない事も影響しているかもしれません。
林:日本舞踊はそういう意味で、コンテンポラリー・ダンスより、ずっと楽しむ方法を見出しやすいと思います。コンテンポラリー・ダンスはいくら沢山見ても、いまだに見方というのはよく分からない(笑)。僕が分からないだけかもしれませんが。一般化できるような体系が無いので作品個別の新奇さへの注目にどうしても傾きがちです。
日本舞踊の場合、流派ごとに紡がれている物語があって、舞踊家の成長過程に立ち会えるのは非常に楽しいと思います。観客と共同体を共にしている意識があると言ったらいいのでしょうか。
ただ、全体としてはバラバラな日本のコンテンポラリー・ダンスも分からないなりにずっと見ていると、自分が特に感応する問題系なりが意識されるようになり、視点が生まれ、独自に文脈を見出しながら作品を面白がれるようになっていきます。
児:舞台から刺激を受け、自分自身の中に発見が生じるのが喜びですよね。この前見たときは何も思わなかったけれども、こうだったのか!って。だから飽きずに劇場通いができる。
林:舞台と客席には共犯関係がありますよね。
児:僕が学生に話すのは、その日の舞台は1回限りで、観客も一緒に作っているものだという事です。今はネットで何でも見られますが、それは撮影者の目を通じて観ている訳で、自分の見方ではない。ライブの楽しさには及ばない事を分かってもらいたい。
三国一(吉村輝章・吉村輝之)
舞踊界の課題
林:作品の上演に対しては文化庁などによる公的助成制度がありますが、成果物の創出を前提にしない実験のプロセスや、実演活動を続けるための補助はほとんどありません。さらに都内でも舞台芸術専用の稽古場というのは片手で済む程度しかありません。「稽古場難民」という言葉があるほどで、コンテンポラリー・ダンスの稽古では大抵、地域の公民館を使う。各自治体が定める条件によっては使用のための団体登録すらできず、自宅や野外で稽古するダンサーもいるほどです。また、公民館は基本的に地域住民の社交場ですから、使用方法にも制限がありますし、地元の方々と予約が競合するので、とにかく稽古場確保には苦労が絶えません。
稽古利用に耐えうる公立施設を設置している自治体もありますが僅かで、都立は水天宮ピット(東京舞台芸術活動支援センター)くらい。評価の難しい創作過程にお金を出すのは難しいのかもしれませんが、プロセスに関わる環境をどう整えるかはとても重要な課題です。ただ公演を打たせ、消費していくだけでは駄目です。
また、先ほど述べたとおり、コンテンポラリー・ダンスでは集団創作を支えるような研究所や稽古場といった独自拠点を持つことができなくなっていますので、腰を据えた密なコミュニケーションや、価値観や理念の共有と醸成といったことがやりにくくなっている。プロジェクトごとのコミュニケーションにはどうしても限界があります。
コンテンポラリー・ダンスが現代芸術として眼差しを向けられている以上、美的なだけではなく、社会や文化的な状況に対してそれぞれのアジェンダ(議題)や批評的視点を持っているのが普通だろうと僕は思います。しかし、そういった活動を支える思考や理念を紡ぐための場所がここ十数年でだいぶ変化しつつあるように感じます。良くも悪くも舞踊家が孤立しているように見えるのです。孤立していればそれぞれ独創的になるかと言えばそうではなく、均質化しがちなのが不思議です。
児:私が日本舞踊の現況で気がかりなのは、流儀の垣根を超え合同の催しが増え、それ自体はいいと思うのですが、各流儀が持ついいものまで削られ、均質化されるのではないかという事です。日本舞踊の良さは様々な流派があって、色々な主張があることも特徴に数えていいと思うのですが。ただ、日本舞踊の定義が分かりにくいところが難しさを感じさせているかな。日本舞踊って何ですかと改めて聞かれると、中々説明しきれないところがあります。
林:確かに、日本舞踊の範疇というのは僕にとっても曖昧です。
舞踊評の衰退
児:私も知る名物的な先生(批評家)方の顔が見えなくなったせいもあるかもしれませんが、舞踊評は沈滞期にあるような気がしています。全部に目を通してはいないから無責任な言い方になりますが、業界の紙媒体が少なくなって批評を発表する場が痩せてきているような印象もあり、それも原因の一つかと思ったりします。インターネットを時々見ますが、実演者からの発信は多いけど、舞踊評を読んだ記憶があまりないなあと。評論家と言われる方たちがどれほどいるのかも知りませんけど、新しい方が育ちにくい環境にあるのではないでしょうか。
日本舞踊に魅力がないとは思いませんが、そもそも伝統芸能自体、一般紙やテレビで取り上げられる機会も減っていますね。これも昔、一般紙に書いていた能評家に、「読者からの反応が無ければ場は減るのは当たり前だ、どんどん意見を投書して欲しいんだよ」、と言われたことがあります。別の機会に古典芸能のプロデューサーから、経済効率優先になって伝統芸能は減らされる傾向にあるとも聞きました。実際のところ、いわゆるゴールデンタイムに伝統芸能が放映される機会などまず無いという感じです。根は同じでしょう。
それはともかく、私も一時、舞踊評を書かせてもらっていました。しかし、だいたいが私のスタンスは「何ごとのおはしますかは知らねども忝(かたじけ)なさに涙こぼるる」で、理屈無しに良いなあというのが最上の評価です。結局は印象評だから、舞踊家のウケは良くなかったんじゃないかな。
舞踊家が求めるのは専ら技術評なんでしょうかね。その大切さは理解するけど、読む方はどうなんでしょう。専門知識がないと作品を受け止められないとなると、そんなに難しく見なきゃならないならと、一般には敬遠されることになるのではと思ったりします。舞踊家は印象評を嫌うかもしれませんが、でも色々な見方があっていいのではないかというのが私の立場です。日本舞踊は面白い、楽しいと思わせて貰えるような文章にも出会いたいな。

林:舞踊と批評は相性が悪いのではないでしょうか。演劇なら作品主題を語り、社会の諸問題と繋げて書くことも容易です。でも舞踊そのものの美や機能について語り、それを第三者に伝えるのはとても難しい。批評や言説が後退するなかで、批評家もライターも一緒くたに広告塔として扱われてしまっているような気がしてなりません。それに、舞踊批評や記事が出て、観客が一気に増えるということもない。
児:舞踊評は必要ですよね。この人は心底踊りが好きなんだな、という評を読みたい。
林:コンテンポラリー・ダンスだとまず若手の批評家というのは皆無です。なので研究者にお願いしたりします。それはそれで有意義ですが、研究者と批評の目線は違う。批評には舞踊を思考する欲望を喚起する機能があると思います。思考するということは舞台で演じる側に支配されず主体的に一歩踏み出すということです。それは広告のように消費する欲望の喚起とは異なりますし、客観的な分析を蓄積する研究者の目線とも少し違う気がする。批評は、作者の意図や事実を越えた想像力を働かせるような、力業だと思うんです。そういう意味での批評家がいなくなっている。
児:難しいのは、能も日本舞踊も1日1回だけの公演が多く、公演評が出ても集客には直接繋がらない。
林:だから事前に記事を批評家に書いてもらったりしますが、それを批評というには憚(はばか)りあります。批評家も気の毒です。舞踊でロングランは難しい。
児:紙媒体が減って、WEBが主流になっていますが、誰に向け書くか。雑誌や新聞はある程度、読者を意識できたと思いますが、WEBだと誰が読んでいるか分からないですね。
今後の「舞の会」
児:先にも言いましたが、「舞の会」は、国立劇場でないとできない催しです。毎年1回ですが、この公演があることで上方舞、地唄舞の舞踊家のモチベーション(意欲)にもなって、継承という点でも大きな役割を果たしていると思います。これを続け、新しい人も舞台に乗せる。そして古典曲継承も大事だけれども、新作もできるといい。
林:僕も新作が今後、どう展開するか関心があります。一方で、むやみに「作品」に傾斜することには抵抗がある。自分のおかれている状況と対比して考えた時、歴史的蓄積を抱えながら、舞踊そのものを継承し、また革新しようとする「舞の会」は様々な学びに満ちています。僕は日本舞踊に関してはまったくの素人ですが、門外漢だからこそ勝手な解釈と応用が可能であるわけです。このような楽しみ方はもっと共有したい。コンテンポラリー・ダンスの踊り手が、日本舞踊のだれそれがどうだったなどと、普通に参照するようになったらなんとも楽しいですよね。逆もしかりで、領域間の交通路がもっと拓けていくことを望んでいます。
編集:飯塚友子(産経新聞記者)
※写真撮影時のみマスクを外しました。
プロフィール
- 児玉信(前石川県立音楽堂邦楽アドバイザー)
- 静岡県生まれ。大学在学中から折口信夫の提唱により設立された藝能学会に入り、機関誌『月刊藝能』(現『年刊藝能』)の編集に携わる。その後、観世流及び金剛流の謡本を発行する檜書店に入社し、観世流機関誌『月刊観世』の編集を担当。能楽のほか舞踊や邦楽公演の企画、執筆など幅広く活躍。藝能学会副会長。近著に『能舞台歴史を巡る』(2018年、建築画報社)。
- 林慶一(d-倉庫)
- 埼玉県生まれ。制作者。2006年より小劇場die pratzeにスタッフとして参加。2005年~2015年は自身のパフォーマンス活動を併行して行う。2012年より「ダンスがみたい!」実行委員会代表。同年、d-倉庫 制作。アーツカウンシル東京 平成29年度アーツアカデミー事業 調査研究員(舞踊分野)。2019年「放課後ダイバーシティ・ダンス」プロデューサー。