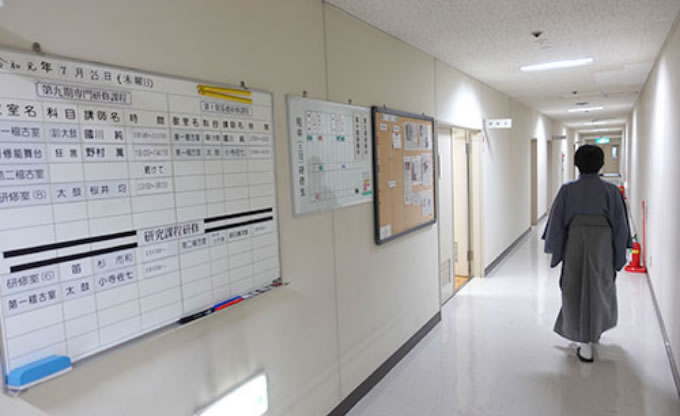研修内容


国立能楽堂は、昭和59年(1984年)の開場当時から、能楽の普及・振興と後継者育成のために、能楽(三役)研修を実施して参りました。令和7年4月現在、第11期研修生(専門研修3年次)、第12期研修生(基礎研修3年次)が日々能楽師となるために研鑽を積んでいます。また、第10期までの研修修了生のうち、31名がプロの能楽師として、舞台で活躍をしております。
研修概要
- 研修目的
- 能楽(三役)になるための基礎・専門教育を行うことを目的とします。
- 応募資格
- 中学校卒業(卒業見込みを含む)以上で、原則として年齢23歳以下の方。
経験は問いません。 - 募集人員
- 若干名
- 選考方法
- 基本的に3年に一度一般公募し、作文、簡単な実技試験、面接を行い選考します。
- 研修期間
- 6年間(基礎研修課程3年、専門研修課程3年)(全日制)
- 研修時間
- 原則として、月曜日から金曜日までの平日午前10時から午後6時まで。
- 研修場所
- 国立能楽堂(東京都渋谷区千駄ケ谷4-18-1)
- 研修内容
- 実技(ワキ方・狂言方・四拍子(笛・小鼓・大鼓・太鼓))
その他(謡・仕舞・講義・舞台実習・楽屋実習・公演見学 等) - 適性審査
- 研修開始後8ヶ月以内に適性を審査し、研修継続の可否を判断します。
- 研修修了後
- 公益社団法人能楽協会に所属し、プロの能楽師として舞台に出演することになります。
- その他
- 受講料無料、教材などは貸与及び支給をします。
遠隔地に居住する研修生には宿舎を貸与(審査あり、有料)、又は住宅費補助金を給付します。
研修期間中、伝統芸能伝承奨励費の貸与資格が与えられます(研修修了後、一定の条件を満たした場合の返還免除規定があります)。
研修生のある一日
基礎研修(3年次)
- 9:30登校控え室で稽古着に着替えます。1限目までは前回の稽古の復習をしたり、今日の稽古の準備をしたりして過ごします。
- 10:40シテ謡
(1限目)観世流のシテ謡の稽古。授業は1コマ
70分。今日は「邯鄲」の稽古です。 - 11:50休憩午後の授業までお昼の休憩です。
- 13:00専科
(2限目)それぞれ専科(笛、小鼓)の稽古。来月行われる発表会の曲を中心にお稽古をします。 - 14:10自習今日は3限目が無いため、空いている稽古場で今日の稽古のおさらいや、付帳や過去の催しの記録などを見て自主稽古をします。
- 16:30講義
(4限目)今日は原典講読の講義です。後日公演を見学する「隅田川」を勉強します。 - 18:00帰宅
青翔会(能楽研修発表会)
青翔会は、国立能楽堂能楽(三役)研修生をはじめ、次代を担う若手能楽師の技能研鑽のための公演です。年に3回催されており、日頃の稽古の成果をお客様にご披露するため、諸先輩たちとともに出演いたします。
研修修了発表会
最終年次(専門研修)の3月に催されます。本公演を以て、全ての研修課程を修了したこととなります。