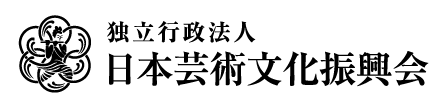イベントレポート
あぜくら特別インタビュー
林 英哲と「日本の太鼓」

林 英哲 さん
日本を代表する太鼓奏者として、国内外で活躍を続ける林英哲(はやしえいてつ)さん。8月の国立劇場特別企画公演「日本の太鼓」では、ご自身の演奏活動五十年を記念して組曲「レオナール われに羽賜(はねた)べ」を演奏していただくほか、英哲風雲の会のメンバーと共に実演も交えて太鼓の魅力を解説していただきます。作品に込めた思い、日本の太鼓について、コロナ禍での活動などについて語っていただきました。
◆西洋の真似ではなく
――演奏活動五十周年、おめでとうございます。
「レオナール われに羽賜べ」は、ご自身が刺激を受けた芸術家をテーマに創作したシリーズの五作目で、洋画家の藤田嗣治(ふじたつぐはる。 1886-1968。フランス帰化後の洗礼名はレオナール・ツグハル・フジタ。)を描いた作品です。演奏活動五十周年、そして今秋国立劇場開場五十五周年の節目の「日本の太鼓」公演に、この作品を選ばれた理由をお聞かせください。
ありがとうございます。
芸術家シリーズの第一作として1998年に写真家マン・レイをテーマにした「万零(まんれい)」を作った頃はまだ手探りで、試行錯誤の繰り返しでした。経験を積んで取り組んだ「レオナール」は、2004年の初演以来お客様の反応も良く、繰り返し演奏することで完成度の高い作品になりました。フランス公演用に太鼓を中心として再構成した改訂版は好評をいただきましたが、この改訂版は、東京ではきちんとした形では上演していませんでしたので、節目の時に相応しいと思い、国立劇場で聴いていただこうと決めました。
――なぜ藤田嗣治を取り上げようと思われたのでしょうか。
藤田嗣治は東京美術学校(現在の東京藝術大学)を卒業して大正時代にフランスへ渡りますが、当時渡欧した日本人画家の多くはヨーロッパの技法を模倣し、日本に持ち帰りました。でも藤田さんは西洋人の真似をせず、独自の技法を編み出そうとトライした。「乳白色の肌」と呼ばれた独特の肌色、日本画の面相筆で描いた線などに、ピカソをはじめヨーロッパの人々が驚嘆したんです。
ところが日本では「西洋受けを狙っただけではないか」とバッシングを受けた。自分たちに引き寄せるのはおこがましいのですが、僕らも海外で評判が良かったと言ってもなかなか理解してもらえない。「祭り囃子の太鼓の何が面白いの?」なんて反応は今でもしょっちゅうです。
西洋の真似ではなく、日本の太鼓を海外で通用するものにしたいという一心でやって来ましたから、藤田さんの思いが僕にはとてもよくわかる。そんなことから藤田さんの人生を作品にしたいと考えました。
――タイトルの「われに羽賜べ」は今様(いまよう)にも謡われていますね。
ええ、大変な苦行である熊野参りを何十回も行った後白河法皇は、〈空より参らむ、羽賜べ若王子(にゃくおうじ)〉、つまり「羽があれば空を飛んで行けるのに」と詠まれました。
藤田さんが晩年を過ごされたパリ郊外のアトリエには天使の絵がいくつも描かれていて、広沢虎造や美空ひばりのレコードがあったのです。藤田さんはフランスに骨を埋める覚悟を決めましたが、「羽が欲しい、自分に羽があれば日本に帰りたい」という熱い思いが、気持ちのどこかにあったのではないかと想像しました。
晩年藤田さんがフレスコ画を手がけたランスにあるフジタ礼拝堂も見学させていただき、その時の印象も作品づくりに活かしています。
◆プロの「打ち手」として
――国立劇場には数多くご出演いただいています。印象や思い出をお聞かせください。
1977年に初回の「日本の太鼓」を客席で観ました。まさか二年後に自分が出演させていただくとは思ってもいませんでした。
初めて舞台に立った時、「こんなに大きな舞台で演奏するのか…」と。間口が広く、天井は高く、巨大な客席が思いのほか近く見える光景。この距離でお客様に見られるのかと、緊張したこともよく覚えています。
演奏者としては、歌舞伎や邦楽の生の音が美しく響くように計算された構造で、音響が素晴らしい劇場です。舞台袖が広いのも太鼓の音を響かせるためにとても良いです。
面白いもので、劇場は経年に従って音が変わっていきます。建物に音が馴染んで良くなっていくのです。劇場は「箱」ですが、「楽器」なのだと実感しています。
――今回は英哲さんと英哲風雲の会の皆さんに、太鼓の解説もしていただきます。
もう二十年ちかく日本や海外の大学で学生たちに講義をしてきましたが、日本の邦楽科の学生でも、芸能としての太鼓の歴史を理解している人は少ないのです。大勢の打ち手が振りを揃えて太鼓を打つスタイルは戦後にできた創作分野であることや、邦楽の中でもほとんど顧みられなかった太鼓の公演をどうやって海外で成功させ、オーケストラと現代曲の演奏が可能になったのかといったことを話しています。
今回は国立劇場のお客様にどうわかりやすく説明できるか、作戦を練らないといけないですね(笑)。楽しみにしてください。
――太鼓という芸能を取り巻く現状についてどのように感じておられますか。
太鼓は今、社会的意義として広がっている部分が大きく、習い事や地域活性化の一環として浸透し、アメリカの大学などでは太鼓のサークルも増えています。
その一方で、パフォーマーとしての太鼓の訓練や質の向上がおざなりになっている現実があります。一生プロとしてやっていけるだけの打ち手がまだ育っていない。
いい打ち方は能率が高く、しかも身体を痛めません。我々は現代のプロの打ち手として、伝統に寄りかからず、常にどうあるべきかを自問自答しながら、作品に反映させるように心がけています。
――今後の展望をお聞かせください。
3月に開催した演奏活動五十周年記念公演では「絶世の未来へ」というタイトルをつけ、私一人で演奏しました。コロナ禍での挑戦でした。これまで毎年海外公演をしてきましたが、今は閉塞状態が続き、なかなか前向きな気分にはなりにくいものです。その中でも希望を見出し、前に進まなければならない。幸い、身体を使って人前で演じることを続けているので、元気でいられています。来年は七十歳になりますが、この先5年でも10年でも今のコンディションを維持したいと思います。
今は、蓄える時期として、情報を収集したり本を読んだりしています。自分の中で発酵させる時間、未来に向けて備える時と捉えています。
――練り上げられた組曲「レオナール われに羽賜べ」、楽しみです。ありがとうございました。