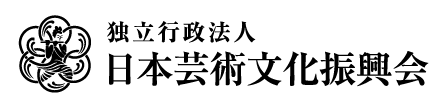国立劇場第45回 特別企画公演 言葉~ひびく~身体Ⅰ「神々の残照伝統と創造のあわいに舞う」(5月25日) 特別対談【前編】
乗越たかお(作家・ヤサぐれ舞踊評論家)& 阿部さとみ(舞踊評論家)
2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、国立劇場とアーツカウンシル東京が令和元年から、3年連続で舞踊&ダンス公演の企画をスタートさせた。皇居に面した歌舞伎や文楽、日本舞踊など伝統芸能の殿堂の劇場が、一体、なぜ。「コンテンポラリー・ダンス徹底ガイド」などの著作で知られる乗越たかおさんと、歌舞伎や日本舞踊など伝統芸能に詳しい阿部さとみさんに、同公演を踏まえ、日本の舞踊とダンスについて、おおいに語って頂いた。(文中敬称略)

左より阿部さとみさん、乗越たかおさん
国立劇場初のコンテンポラリーダンス~評論家2人とも「画期的」
乗越(以下、乗):今回の公演はさまざまな意味で画期的ですよね。コンテンポラリー作品が国立劇場で上演されたのは、初めてのことではないでしょうか。しかも石井達朗さん(舞踊評論家、慶応大名誉教授)が企画アドバイザーで入っているのが素晴らしい。舞踊評論家といっても、海外に自分で足を運んで、幅広く色々なジャンルをご覧になっている人は本当に少ないのですが、石井さんはその数少ない中のお一人ですからね。
〈今シリーズは、世界の舞踊に詳しい石井氏が企画アドバイザーを務め、全体を貫くテーマとして「〝言葉〟と〝身体〟の持つ力と魅力を伝える」を掲げる。1回目は「神」をキーワードに、日本舞踊「翁千歳三番叟」、インド古典舞踊「オディッシー」、トルコ舞踊「メヴラーナ旋回舞踊(セマー)」。そして最後にコンテンポラリー・ダンスの新作「いのちの海の声が聴こえる」が上演された〉
乗:こうした様々な舞踊を並べる公演は、「いろいろ見られたお得感」で終わりがちですが、今公演は企画段階で相当に練られていますね。まず全体を通して「聖なるもの」という共通の切り口がある。現代社会から、「聖なるもの」はもっとも遠くなっているのではないか-という問題提起が、「残照」というタイトルにも繋がっているのでしょう。各国の伝統舞踊とも、発せられる言葉の響きが重要な役割を果たし、ライブで音楽を演奏していたのも素晴らしかった。
阿部(以下、阿):各国の伝統舞踊とも、共通して「人々が神に何を求めているのか」「われわれにとって神とは何か」が感じられました。日本の伝統芸能においては、神に捧げるものから、(能の「翁」のように)神に扮するもの、神に降りてきてもらうもの、という考え方もあります。3演目それぞれ、神とは何か、現代人が多方面から考えるヒントになる企画だと思いました。
乗:アニメのオタクの方々が、作品ゆかりの地を巡ることを〝聖地巡礼〟と称し、「凄い」という意味で「尊い」って言いますよね。
阿:今の若者たちは、普通に「神だ!」「降臨した」「神対応」などと言っています。
乗:従来の意味での「神」という形を取ってなくても、宗教的なマインドは、意外に今も身近に息づいているのかもしれませんね。
伝統舞踊とコンテンポラリー・ダンスは繋がっている?!
乗:コンテンポラリー自体、歴史は30年くらいです。1970~80年代、仏独ベルギーを中心に盛り上がった。80年代の日本はバブル経済でしたから、そういう海外アーティストをバンバン招聘したので、リアルタイムで最先端のダンスをまとめて見ることができた。それは「新しいダンスの楽しさ」だと興奮していたわけですが、やがて「新しいけれど、面白くないもの」が山ほど出てきた。すると別に「新しいから面白かった」わけではなく、「面白いダンスは時々、新しさをまとう」だけのことだった、と後から気づくことになったわけです。そんな「新しさ至上主義」に狂奔していたとき、一番冷遇されたのが伝統舞踊や民俗舞踊でした。「だってあれは受け継いでいるだけで、何も新しいことをしていないよね」と(笑)。
阿:身も蓋もないいい方(笑)
乗:しかしコンテンポラリーも黎明期の「新しさ至上主義」熱が一段落してくると、伝統舞踊や民俗舞踊のことも冷静に見られるようになる。そして「何百年も生き残り続けている伝統舞踊の強さって凄くない?」と気づき、今は大いに見直されています。

世界的に人気のダンサー・振付家で言えば今、スペイン舞踊で新しい取組みをしているイスラエル・ガルバンや、英振付家アクラム・カーンですね。カーンはロンドン生まれですが、両親はバングラデシュ出身で、子供の頃から北インドの伝統舞踊を本格的に学んで、作品にも活かしています。今、一番人気のベルギーのシディ・ラルビ・シェルカウイは父親がモロッコ人ですが、彼自身、とにかく身体が利いて何でもできてしまう。世界各地の伝統舞踊のダンサーと、コラボレーションする作品を次々に発表しています。
ただ、これらは成功している例ですが、伝統舞踊の方が、表層的な新しい試みをしようとしてサムい結果になることも少なくないですよね。
阿:私から見ても、日本舞踊で古典を古典として定式に沿って踊ったら素敵な表現力のある舞踊家なのに、ちょっとひねってやってしまったために「あぁ~」と残念に思う事はありますね。
乗:「何で日舞にタンゴを入れる必要が?」みたいな舞台ありますね(笑)。ガルバンは「フラメンコの革命児」と言われていますが、彼自身は革命をしているつもりはない。正当な伝統舞踊を踊っているつもりなんです。ただ彼が内に抱える表現世界があまりにも大きいので、外部の人が考える伝統舞踊の枠を、はみ出しているだけのことです。そういう大きな表現世界を抱えたアーティストが、最先端のダンスを更新していく。その際には伝統舞踊の力も、ダンスの最前線で大きな力を発揮していくことになるでしょうね。
今回の企画は、そういう世界的な最先端のダンスのトレンドが背景に生きていると思います。こうした企画に、新国立劇場ではなく国立劇場が取り組み、また伝統舞踊とコンテンポラリーという組み合わせを持ってくるところが慧眼です。各舞踊に共通するコンセプトも明快で、さすがの企画だと思いました。

阿:伝統も最初から伝統だった訳ではなく、昔の人々が「素敵だな」と思った気持ちから再演が重ねられて、その作品や芸能が今まで繋がって、伝統になっていった。伝統だから護っていこう、という方向ではないはずです。昔の日本は著作権などがなく、パクリOKだったじゃないですか。その結果として、素晴らしい作品や芸能が生まれている。伝統といっても新しくない訳ではなく、いい物を取り入れて続けていった結果で、先人の知恵の集大成ですね。
各演目を振り返る~「翁千歳三番叟」
〈長唄「翁千歳三番叟」は、能「翁」に基づき、天下太平・五穀豊穣を祈る神々が登場。出演は尾上墨雪(翁)、花柳寿楽(千歳)、若柳吉蔵(三番叟)〉
阿:「三番叟」は能楽の「翁」をもとにしたものが歌舞伎舞踊に取り入れられ、そこから様々に展開しました。今回の「翁千歳三番叟」は厳かでしたが、「操り三番叟」などのユーモラスなものなど、その他の色々なものを含めて「三番叟物」と呼ばれる作品群が生まれました。面白く楽しく見ようっていう流れですよね。
乗:今回の「三番叟」、今まで見てきたものとはなにか違う感じがしたのですが、なぜでしょう。
阿:まず舞台面が違いましたね。
〈通常の「三番叟」は能舞台をかたどった「松羽目」が背景になるが、今回は屏風をモチーフとした縦吊りのオブジェに、松竹梅をあしらった美術だった〉

翁千歳三番叟
阿:背景の美術にまず、目が吸い寄せられました。特定の流儀の物ではない演目ですから、許可なく自由にできる面もあると思います。今作の背景は、賛否両論だと思いますが、新しい事をやるとそうなりますよね。
乗:木ノ下歌舞伎(京都を拠点に、木ノ下裕一が主宰。歌舞伎演目を現代的視点で上演している)で、役者がスニーカーを履いて「三番叟」をやっていましたね。あれも彼らは「ちゃんと研究し、本行に基づいた上での今日的な表現」と言っていますが、僕はとても良いと思います。

尾上墨雪
阿:「三番叟」は、もともと大きく変えることはほとんどない決まり物です。面そのものを神体と考え、神様に来て頂き、面をかけることで役者は神自身を演じます。
乗:神様に踊りを捧げるんですか。それとも降りてきて頂くのですか。
阿:翁の面に神が宿っている、つまりそこに神が来て下さる。翁の役者は「おこがましくも、神の役を勤めさせて頂きます」という意味で、舞台上でお辞儀をしますが、今日の観客は、そこで拍手をしてしまう。お辞儀されると拍手をしてしまう日本人の習慣ができてしまいました。
乗:バレエでも、ダンサーがクルクル回ると反射的に拍手が起きますね。ときに「そういうシーンじゃないだろう!」という場面でも。
実は個人的に「三番叟」でまず目を引いたのが、後見の方でした。後ろで、演者に椅子をスッと出したりする人。あの動きの滑らかさ! スルスルといつの間にか来ていて、所作に一切のムダがなく、全てが完璧なタイミングで、じつに美しい。見惚れました。
バレエ作品では大概、主人公のカップル以外は「その他大勢」です。ところがコンテンポラリーでは、ダンサーに役割自体ないことが多い。米振付家のマース・カニンガム(1919~2009年)の作品などは「舞台上は平等でフラットな空間で、どこを見るかは観客が決める」「舞台上に中心を作らない」等、革命的な変化をもたらしました。
ダンスは本来自分で踊って楽しむ物です。しかし舞台芸術としてのダンス、特にバレエなどは「特別な才能のある人が、特別な訓練を受けて実現する美の世界」です。素晴らしい芸術です。しかしその過程で、色々な可能性を捨てているのではないか。そうした可能性のひとつひとつを「いや、こういうのも面白いんじゃない?」と発見し、そのリアリティを描き出すのがコンテンポラリー・ダンスです。人間の身体はひとり一人すべてが唯一無二の存在だから、それぞれの身体にしかできない動きを見つければいい。「このステップができるのから素晴らしい」ではなく、「自分にしかできない動きを発見するのが大事」という考え方です。主役をみんなで支えるのではない。
だから僕も、舞台の隅っこを見る癖がついているのかもしれません。それで「三番叟」の後見のおじさんが格好いいなあと思う。これは僕の見方がひねくれているのでもないし、演者を軽んじているのでもありません。ダンサーだけでなく、後見の無駄のない動きも含め、舞台上にいるすべての人が美しいと感じ、何倍も楽しめました。
阿:翁を勤めた尾上墨雪(日本舞踊尾上流前家元)は、素踊りをすることが多く、今回のように化粧をして、衣裳付けで踊ることが珍しいので、私はまずそれが新鮮でした。ですから公演を見逃した人は悔しがっていましたよ。格好良かったですし、もちろん翁として相応しく、品格があって重厚で、最高位の神を演じるにふさわしいと思いました。体も利きますし、安心して見られる。舞踊家として充実期だと思います。花柳寿楽の千歳は折り目正しく、端正でした。

花柳寿楽
若柳吉蔵演じる三番叟は、そもそも躍動感があって目立つ役ですし、動きが弾むようで、三番叟らしさがあり、3人ともそれぞれの役どころをしっかりと押さえていました。

若柳吉蔵
ただ私は、全体的に舞台美術が気になって、演者が背景に溶け込んでしまった部分もあったと思いました。通常のシンプルな松羽目で、見せてほしかったかな。古いのでしょうか。
乗:バレエやミュージカルは、ド派手な舞台装置がある前提で、それに負けない身体のあり方を追求してきた歴史がある。それぞれの踊りで、ちょうどいいサイズ感や濃淡があるだろうから、簡単ではないでしょうね。
阿:空間の使い方の違いみたいなものですかね。それにしても日本人は踊りが好きですよね。こんなに色々なダンスが、一つの国の中にあるっていうのは世界的にも珍しいのではないでしょうか。日本舞踊一つとっても色々あって、こんなに沢山の舞踊がある国も、そんなにないのではないか。民俗芸能、能狂言、雅楽、歌舞伎、海外のバレエも大好きだし、ハワイアンも好きですよね。
乗:習うのは好きなんですよね。昔の清元もそうですよね。
阿:お稽古事文化で、自分がやるのは好きなんですよね。
乗:今、盆踊りも「bon dance」とか「にゅ~盆踊り」として盛り上がっていますね。現代に残っているダンスも、神様への奉納とか歴史的背景はいろいろあるでしょうが、要はその地域の人がカッコイイと感じるなかから取捨選択され、踊り継がれてきたわけですよね。
阿:私もやりたい!という踊りですよね。(つづく)
編集:飯塚友子(産経新聞記者)
※後編はこちら。
プロフィール
- 乗越たかお(作家・ヤサぐれ舞踊評論家)
- 株式会社ジャパン・ダンス・プラグ代表。06年にNYジャパン・ソサエティの招聘で滞米研究。07年イタリア『ジャポネ・ダンツァ』の日本側ディレクター。日本とソウルで5つのフェスティバルのアドバイザーを務める。『コンテンポラリー・ダンス徹底ガイドHYPER』(作品社)、『ダンス・バイブル』(河出書房新社)、『どうせダンスなんか観ないんだろ!?』(NTT出版)、他著書多数。現在、月刊誌「ぶらあぼ」で『誰も踊ってはならぬ』を連載中。
- 阿部さとみ(舞踊評論家)
- 日本アイ・ビー・エム株式会社在職中に歌舞伎、日本舞踊の面白さに目覚め、日本大学芸術学部、及び早稲田大学大学院文学研究科で学ぶ。文化庁芸術祭執行委員、文化芸術による子供の育成事業巡回公演事業企画委員など歴任。月刊「日本舞踊」に「リボンの夢」、「東京新聞」に「花に舞い踊る」を連載中。共著に『忠臣蔵』(赤穂市)、『歌舞伎登場人物事典』(白水社)、『歌舞伎と宝塚歌劇』(開成出版)など。