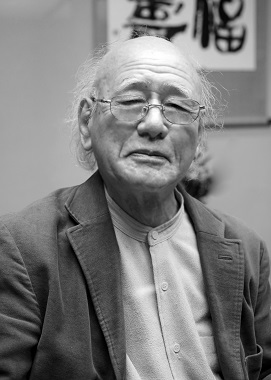
- 西角井正大(民俗芸能研究者)
- 国立劇場の草創期を知る方に貴重なお話をうかがう「国立劇場草創期」。第7回目のゲストは民俗芸能研究者の西角井正大さんです。西角井さんは神道宗教学・芸能民俗学者の西角井正慶さんの三男として、昭和7年(1932)大宮の氷川神社の社家に生まれました。國學院大学大学院を修了後、昭和36年(1961)文部省文化財保護委員会無形文化課に入省。国立劇場創設に尽力され、開場とともに国立劇場に移り、民俗芸能公演の制作を担当し、現在の公演の基礎を構築されました。退職後は大学で教鞭をとり、現在も研究されています。
(この記事は、会報「あぜくら」令和4年(2022)5月号に掲載された特別インタビューを、ご好評につき再録するものです。)
民俗芸能との出会い
コロナ禍で、祈りや信仰と共に民俗芸能が見直されているようです。
コロナウイルスの感染で世界中の人が大変な生活を強いられていますが、終戦直後の日本は本当に何も無くて、民俗芸能どころではなかった。しかし、戦地から帰ってきた兵隊が拠りどころにするのは、自分のふるさとの祭りであり芸能でした。民俗芸能は、日本人の魂の拠りどころだと思います。
私の生家は代々大宮の氷川神社の社家でしたが、国の直営の官幣大社になり、社家制度が廃止になったので、父は神主にならずに國學院大学で折口信夫先生の門下になりました。私も國學院大学に進学しました。大学で英文学を教わった丸谷才一先生(文化勲章)は、「僕が國學院に来たのは、折口先生がいらしたから」と仰っていました。実際に折口先生の授業を受けられなかった私は没後の弟子です。生まれ育った環境もありますが、民俗芸能に魅かれたのは折口先生の影響ですね。本田安次先生(文化功労者)や民俗芸能研究家の三隅治雄先生などのご指導も仰ぎました。
「いつ建つ劇場」が「国立劇場」に
国立劇場開場前のお話をお聞かせください。
卒業のころは学生運動が盛んで、入省時の口頭試問では、思想問題を厳しく聞かれました。私は親の七光りもあって、昭和36年(1961)に文部省文化財保護委員会無形文化課に採用されました。昭和30年(1955)9月に芸能施設調査研究協議会が設置された後も、劇場がいつ出来るのか判らず、国立劇場法もなかなか出来なかったので、当時「国立劇場」は「いつ建つ劇場」などと揶揄されていました。
当初の劇場の設計図は1,300席ぐらいの劇場と事務棟に300席くらいの講堂が付いたものでした。その劇場と事務棟をひとつにつなげて、講堂を630席の小劇場にしたのは、後に国立劇場の雅楽・声明担当プロデューサーになる木戸敏郎さんです。私も、大劇場の直径約20メートルの三杯飾りの廻り舞台の図面を描きましたよ。新しい事を始めるには、周到な理論武装が必要で、意見を通すために、どれだけ膨大な提案書を書いたことか。
あぜくら造りの劇場
昭和37年(1962)に公募した国立劇場の設計競技には、307点もの応募があり、岩本博行氏(大阪・竹中工務店)の作品が選ばれました。今のあぜくら造りの建物です。今でも思うのですが、国立劇場は、ただのビルでは駄目なのです。建築物そのものが、日本の文化・芸術のモニュメントでなければならないのです。今度の建て替えで、外観がどうなるのか分かりませんが、あぜくら造りでなくなったとしても、この点だけは忘れないでほしいですね。
開場記念公演と思い出深い公演
昭和41年(1966)12月、第1回民俗芸能公演「壬生狂言」が上演されました。
民俗芸能公演の一番の課題は、有料公演にふさわしい舞台を創ることでした。
そこで朝日新聞の天声人語でも取り上げていた「壬生狂言」に白羽の矢を立てたのです。壬生寺の貫主松浦融海さんも、講中の方々も、劇場の舞台でやるのは初めてだったのに、快く引き受けてくださいました。

開場記念公演 第1回民俗芸能公演「壬生狂言」 昭和41年(1966)12月
終戦直後から民謡ブームで、彼方此方に民謡酒場が出来ました。「日本の民謡」はそのブームを反映した企画でした。町田佳聲、三隅治雄、竹内勉など諸先生の助力を得て、大劇場で8回公演しました。中でも北前船をテーマにした、昭和45年(1970)年8月の公演は好評でした。町田先生が、ハイヤ節を沖縄から海運と一緒に伝えた人がいると「東洋音楽研究」で発表なさった。それを舞台にのせたのです。歌舞伎の『博多小女郎浪枕』の毛剃九右衛門は、アイヌの厚子を着て船に乗っているでしょう、あの世界です。
大きく羽ばたいた「日本の太鼓」
「日本の太鼓」を始めるときも、大反対されました。1年かけて、60枚ぐらいの論文を書きました。ところが、最初の「日本の太鼓」の評判がとてもよかったので、あんなに反対されたのに、公演はシリーズ化しました。

第26回民俗芸能公演「日本の太鼓」 昭和52年(1977)9月
「御諏訪太鼓」小口大八
民俗芸能として代表的な「御陣乗太鼓」、神楽太鼓から創作された「御諏訪太鼓」などを取り上げました。また、新しい試みとして、それぞれにルーツを持つ打ち手4人によるグループ「鼓韻の会」を結成して新作を発表しました。この公演に多く出演してくださった林英哲さんは、日本の太鼓を民俗芸能から舞台芸術にした創始者です。
琉球芸能についてもお聞かせください。
大正10年(1921)に琉球の宗教を研究するために沖縄に行かれた折口先生は、そこで琉球・沖縄の芸能に出合い、昭和11年(1936)には沖縄から芸能団を呼びました。私は、折口先生が沖縄のことを「血を分けた兄弟の島」と仰ったことに感銘を受けたのです。昭和42年(1967)1月、最初の「御冠船踊」のときは、まだ沖縄は返還前で外国でした。打合せで沖縄へ行くのに、パスポートと渡航証明書を申請しましたが、スタッフの1人が戦争中捕虜収容所の通訳をしていたのでC級戦犯扱いになり、パスポートが出発日の早朝に取れてホッとしたこともありました。

第1回琉球芸能公演「御冠船踊」 昭和42年(1967)1月
「組踊 万歳敵討」高平良御鎖の厄落としの浜下りの遊宴の場
新潟の瞽女唄、アイヌ・オロッコ・ギリヤークの芸能、綾子舞等々。国立劇場の民俗芸能公演の記録は今では貴重なものになりました。これからの民俗芸能は、日本の個性を維持することが大切です。無個性ではしようがない。芸能の専門知識はもちろんですが、伝統芸能が日本の個性の中でどういう位置にあるかを考えられる人が、劇場には必要ですね。

第11回民俗芸能公演「アイヌ、オロッコ・ギリヤークの芸能」 昭和46年(1971)3月
「ケオマンテ(御霊送り)」
興味深いお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。
(取材 あぜくら会)
